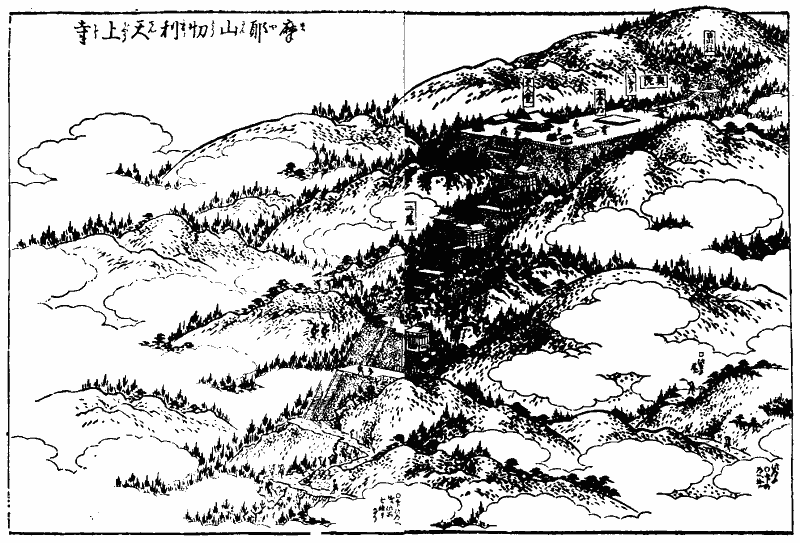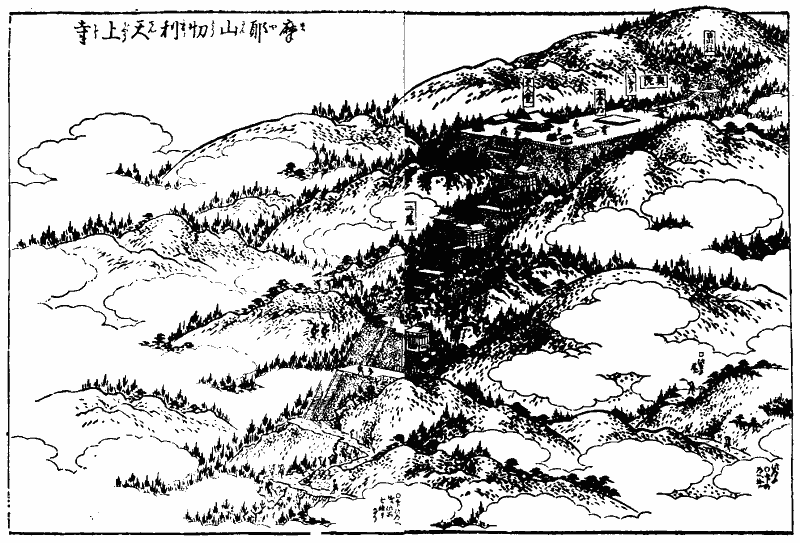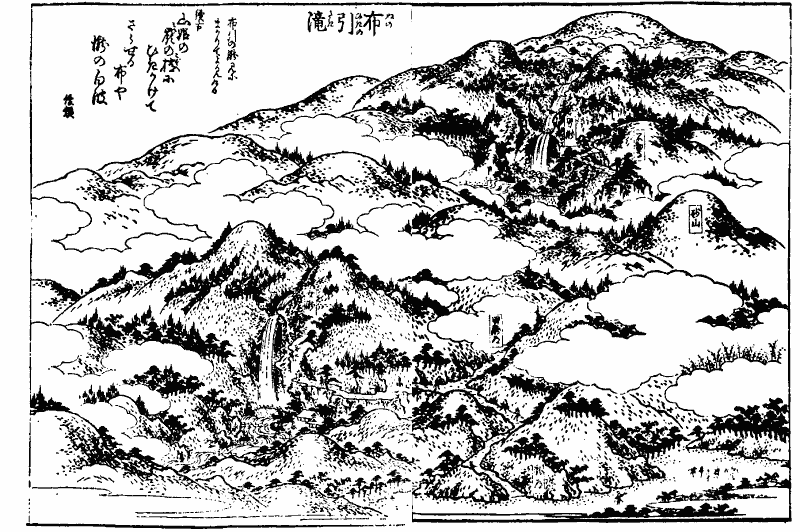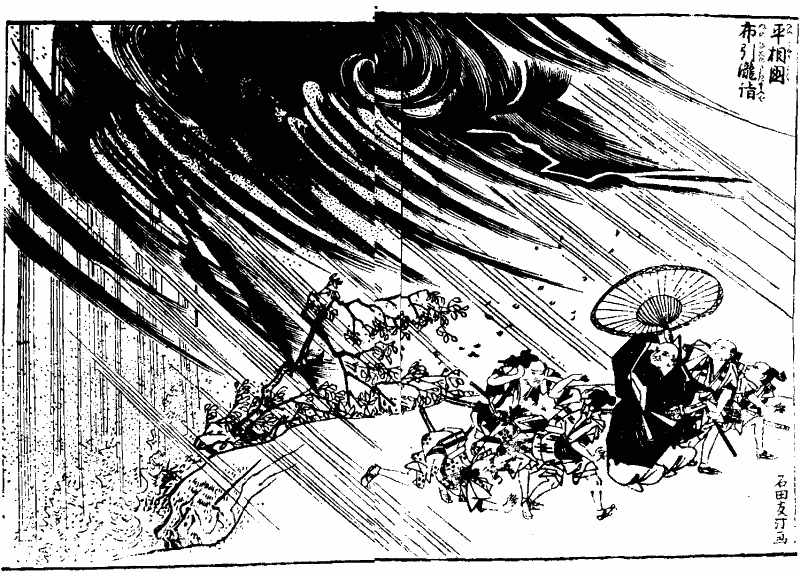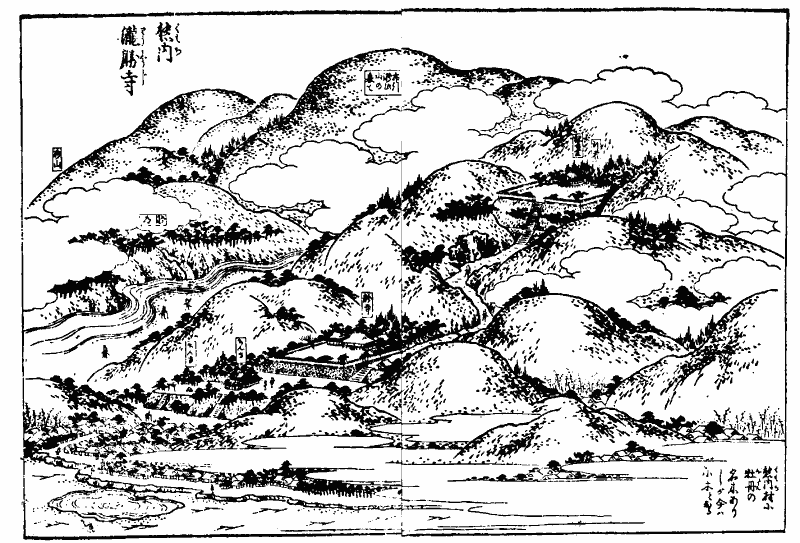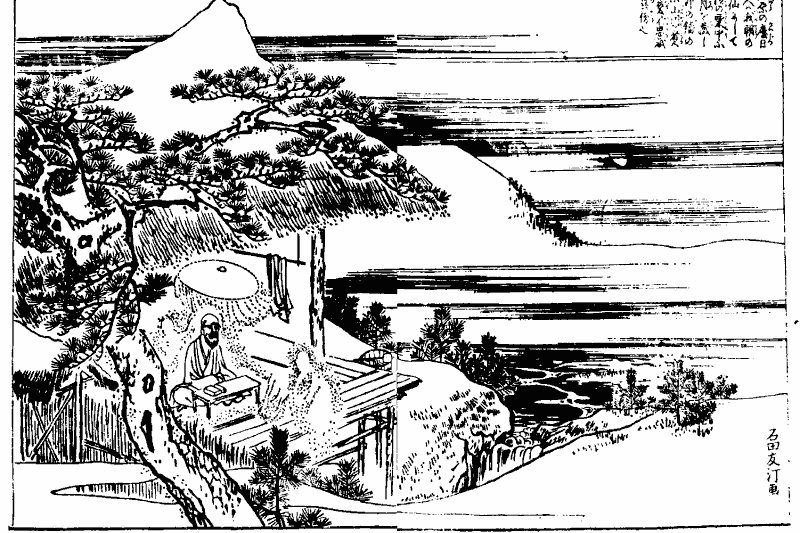|
布曳滝[布引の滝]
砂山にあり。雌滝・雄滝のニ流ありてあひ距つ事三町ぱかり、ともに岩面を流れ落つる事白布を曝ずに似たり。雄飛泉[おだき:おんだき]の高さニ十四丈、五段に折りて落つる。雌曝泉[めだき:めんだき]の高さ十八丈、同じく布を曳くに異ならず。地勝景偉衆郡最一の美観なり。飛泉の東に一つの小丘あり。
これを望滝台といふ。飛泉の水源、武庫山より流れて末は生田川と成る)
『栄花物語』布引滝巻
その頃、との、ぬのびきの滝御らんじにおはします。道のほどいとをかしう、さまざまの狩装束などいふかたなし。業平がいひつづけたるやうにぞありけむかし。
さらしけんかひもあるかな山姫の尋ねてきつるぬの引の滝 くわんぱくどの
水の色ただ白雪とみゆるかなたれさらしけん布引の滝 皇后宮太夫 顕房
めづらしき雲井はるかにみゆるかなよに流れたる布曳の滝
皇太后宮太夫 祐家
雲井よりとどろきおつる滝つせはただ白糸のたえぬなりけり
皇后宮権太夫 経信
水上の空にみゆれば白雲のだつにまがへるぬのびきのたき
三位中将 師通
立ち帰り生田の杜のいくたびもみるともあかじ布引の滝
権中将 雅実
よとともにこや山姫のさらす成る白玉われぬ布引のたき
中将 公実
水上は霧立ちこめてみえねども音ぞ空なるぬのびきの滝
播磨守為家
いくひろとしらまほしきは山姫のはるかにへたる布引の滝
いへつな
『伊勢物語』云ふ、
このをとこなま宮づかへしければ、それをたよりにて、ゑふのすけどもあつまりきにけり。このをとこのこのかみもゑふのかみなりけり。そのいへのまへの海のほとりにあそぴありきて、いざ、この山のかみにあるといふ布引の滝見にのぼらんといひて、のぼりて見るに、その滝、ものよりことなり。(李白が魔山濠布の詩に、飛流直下三千尺、疑ふらくはこれ、銀河の九天より落つるかと。これ文勢なり)。長さ二十丈、ひろさ五丈ばかりなる石のおもてに、しらぎぬにいはをつつめらんやうになんありける。さるたきのかみに、わらうだのおほきさして、さし出でたる石あり。その石のうへにはしりかかる水は、せうかうし、くりのおほきさにてこぼれおつ。そこなる人にみな滝の歌よます。かのゑふのかみまづよむ、
芦のやのいさごの山のそのかみにのぼりて見れぱ布引の滝
我が世をばけふかあすかとまつかひのなみだの滝といづれたかけん
あるじ、つぎによむ。
ぬきみだる人こそあるししら玉のまなくもちるか袖のせぱきに
とよめりけれぱ、かたへの人、わらふことにやありけん、この歌にめでてやみにけり。
『続古』
山人の衣なるらし白妙の月にさらせる布ぴきのたぎ
後京極摂政
『千載』
水の色のただ白雲とみゆるかな誰さらしけんぬの引の滝
六条右大臣
『新古今』
久方の天津乙女の夏衣雲井にさらす布びきの滝
有家
『詞花』
雲井よりつらぬきかくる白玉をたれ布引の滝といひけん
隆季
『夫木』
布引の滝の白糸夏くれぱ絶えずぞ人の山路たづぬる
定家
|